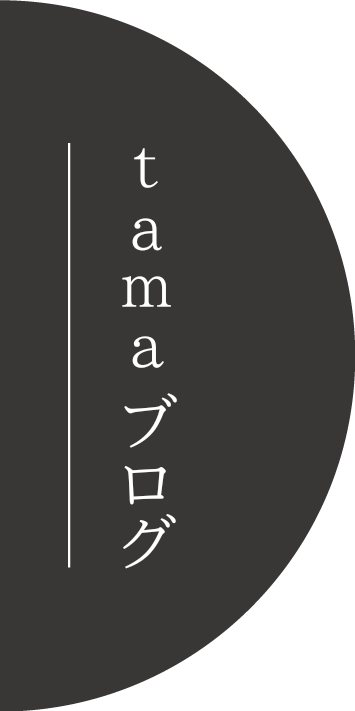こんにちは、たま企画室です。
お正月気分もそろそろ落ち着いてきた頃かと思います。本日は、日本の伝統行事の一環である松の内(まつのうち)の終了と、それに伴う正月飾りの片付けについてお話ししたいと思います。
松の内とは?
松の内とは、門松やしめ飾りなどのお正月飾りを飾っておく期間を指します。この期間は年神様が家に滞在しているとされ、とても神聖な時間です。
- 関東地方では1月7日まで
- 関西地方では1月15日まで
本日は松の内の終了日(関東地方)となります。お正月飾りを片付けるタイミングとして最適な日です。
正月飾りの片付け方
正月飾りには年神様が宿っているとされるため、正しい方法で片付けることが大切です。
- タイミングを守る
松の内が終わった後、1月7日または15日を過ぎたら片付けを始めます。 - どんと(どんど)焼きに持参する
片付けた門松やしめ飾りは、地域の神社や自治体で行われる「どんと焼き」や「お焚き上げ」に持参するのがおすすめです。炎で清めることで、神様をお送りし、新しい一年の無病息災を祈ります。 - どうしてもゴミとして処分する場合
焼却できるゴミとして処分する場合は、塩で清めてから白い紙に包むと良いとされています。
毎年、どんと焼きで見受けられるのが、正月行事に関係のないものを持ち込む方々です。見かけるたびに、少し寂しくなります。どうか、そうしたことは避けていただき、正月飾りに限らず、心を込めて片付けをしていただけると幸いです。
鏡開きについて
正月飾りを片付けた後に行うのが鏡開きです。鏡餅を割って食べることで、年神様の力をいただき、一年の健康や幸せを願う行事です。
- 鏡開きの日程
- 関東地方:1月11日
- 関西地方:1月15日(小正月)
- 鏡餅を割る際のポイント
鏡餅は包丁で切るのではなく、木槌や手で割るのが伝統的です。「切る」という表現は縁起が悪いとされ、「開く」と表現することで末広がりの幸運を祈ります。 - 食べ方
割った餅は、お汁粉やお雑煮としていただくのが一般的です。年神様の力を体内に取り入れるという意味があります。
ちなみに我が家の鏡開きは1月11日です。食べ方については、お正月にお雑煮をたくさんいただいたので、鏡開きでは焼き餅として食べることが多いです。
正月飾りを片付け、鏡開きをする意味
日本の正月行事は、年神様を迎え、もてなし、そしてお送りする一連の流れがあります。
- 飾りを片付けることで年神様をお見送りし、新しい日常へと切り替えます。
- 鏡開きでは、年神様からの恩恵を体内に取り入れ、一年の健康や繁栄を願います。
こうした行事を丁寧に行うことで、日本の伝統を守りながら、心を新たに一年を始めることができます。
お正月行事を終える準備を楽しみましょう
松の内の終了に伴う片付けや鏡開きは、決して面倒なものではなく、年神様への感謝を形にする大切な儀式です。家族や大切な人と一緒に行いながら、新しい一年の目標や願いを話し合う時間にするのも素敵ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!何かご質問やご意見がありましたら、ぜひお気軽にコメントやお問い合わせください。
今年もたま企画室をどうぞよろしくお願いいたします!
なお、この記事はこれまでに得た知識をベースに、私の見解や個人的な体験に基づいて書かせていただいております。もし内容に関して気になる点や誤りがあれば、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様のご意見やフィードバックは、今後の改善にとても参考になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。