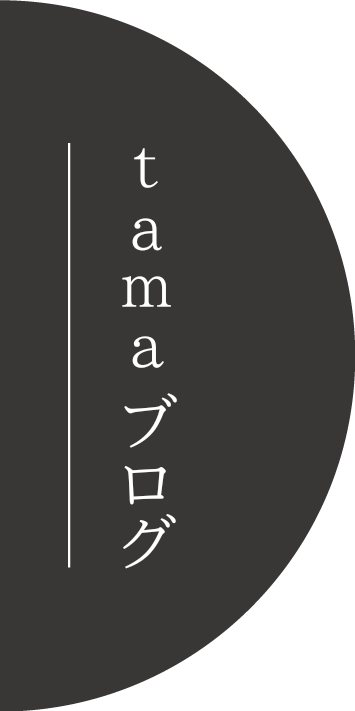こんにちは、たま企画室です。
今日は【石造美術】についてお話ししたいと思います。
今回ご紹介するのは宝塔です。ちょうど石材店様から「石造宝塔を提案してほしい」とのご依頼をいただき、依頼内容の条件を伺う中で、ある宝塔が頭に浮かびました。それが、大分県豊後大野市の【蓮城寺宝塔】です。
この宝塔は意匠が特徴的で、今回のご依頼にも合うのではないかと考えました。そこで今回は、この蓮城寺の宝塔について詳しくご紹介し、現在進行中のご提案については改めて後日、ブログにてご紹介させていただこうと思います。
蓮城寺には、同型式・同寸で意匠まで共通する石造宝塔が二基、境内に並列して建てられています。向かって右側の塔の塔身には銘文の一部が残っており、それにより永仁四年(1296年)、鎌倉時代後期の造立と推断されています。


この宝塔を初めて見たときの印象は、「どっしりしてるな~」でした。写真をご覧いただくとわかるように、基礎と屋根がかなり低めに作られています。そのためか、塔身は他の石造宝塔より大きく作られ、全体として安定感と重量感のある構成となっています。
この塔で最も「おっしゃれ〜!」と感動したのは、近づいて初めて気づくくらい浅く彫られた基礎天端の蓮弁でした。あまりにも素朴で、思わず「本当に鎌倉後期の作なの?」と疑ってしまったほどです。


ところが、それとは対照的に、下部のふっくらとした樽形の軸部と、その上にすっと絞られた首部から成る塔身部分に施された彫刻は、驚くほど緻密。軸部には四方に扉や柱、長押(なげし…和室の壁面をぐるりと囲む化粧部材)が丁寧に彫られ、扉と扉の間には四仏の種子が彫刻されています。
首部は2段構成で、下段には斗栱や高欄、上段には扉型の意匠がしっかりと再現されています。




屋根はこれまた、素朴すぎるというか、「いいの?」と思うくらいに意匠がありません。通常ですと、降棟(くだりむね…屋根の大棟から、屋根の流れに沿って軒先方向に降ろした棟)や垂木(たるき…棟から軒に渡して屋根面を構成する材料)、隅木(すみぎ…隅棟の下にあって垂木の上端を受けている斜めの材料)などを彫刻する、いわば“腕の見せ所”なのですが、なぜか薄い露盤(屋根の頂部に突き出た平らな部分)のみです。この意匠のアンバランスさが、なんともおもしろいですよね~。
全体を通して感じたのは、塔身がまるで木造宝塔をそのまま石に写し取ったかのような丁寧なつくりである一方で、それ以外の部分は素朴な印象を受けるという、対照的な特徴です。そして、基礎の素朴な蓮弁と塔身に刻まれた精巧な意匠がひとつの塔の中で共存している、その「温度差」のようなものに、気づけばすっかり心をつかまれていました。
以上【蓮城寺宝塔】(二基)の魅力を簡単にお話ししましたが、うまく伝わったでしょうか?いくつかの専門用語が登場しましたので、これらについても後日詳しくご説明できればと思います。
この記事では、私なりに理解した石造美術について書かせていただきました。
内容に関して気になる点やご意見がございましたら、ぜひお気軽にコメントやお問い合わせいただけますと幸いです。
皆様からのフィードバックは、今後の改善にとても役立ちます。
今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。
参考文献 望月友善著 「大分の石造美術」『木耳社』昭和59年9月30日
「日本石造物辞典」『吉川弘文館』平成24年12月10日
多田隈豊秋著 「九州の石塔 下巻」『西日本文化協会』昭和53年2月23日