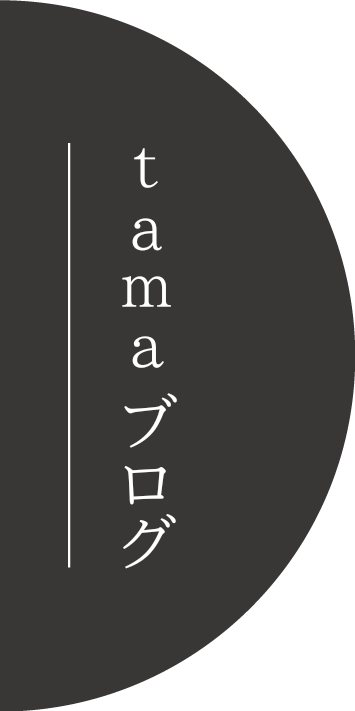こんにちは、たま企画室です。今日は【石造美術】についてお話ししようと思います。
とり上げるのは【宝塔(ほうとう)】という仏塔(石塔)です。その中でも、私にとって特別な存在であり、言葉を選ぶなら人生を変えるきっかけとなった一基をご紹介したいと思います。
その石塔は愛媛県今治市にある【満願寺宝塔(まんがんじほうとう)】(鎌倉時代後期)です。
まず、宝塔の形式についてお話しします。石造宝塔の本体は下から順に基礎(きそ)、塔身(とうしん)、屋根(やね)、相輪(そうりん)の4つの部材で構成されています。形式は宝篋印塔と同じですね。【満願寺宝塔】は本体以外に台座と基壇が設けられていますが、以前のブログで紹介した【西大寺奥ノ院五輪塔】同様に、それらは塔として必ずしも必要なものではなく、塔を荘厳(しょうごん…仏像や堂宇、石塔などを美しく厳かに飾りつけること)するために設けられたものです。

さて、【満願寺宝塔】の見所ですが、正直言って全てが魅力的であると言いたいところですが、その中でも特に際立っているのが基礎部分です。側面の3面は、四角く囲む輪郭を巻き、その内側に格狭間(こうざま)が彫刻され、1面は素面となります。この格狭間は地域や石工、時代によってさまざまなデザインが見られますが、特に【満願寺宝塔】のものは私好みで魅力的な型です。また基礎上部は、平面円形で単弁の反花座が彫刻されており、全国的にも非常に珍しく、見応えがあります。その精緻な彫刻や構造は、一見の価値が十分にあります!以前ブログで紹介した【奈良国立博物館宝篋印塔】の基礎に通じるものがありますね。


そして塔身ですが、こちらも地域や石工によってさまざまなデザインが見られますが、【満願寺宝塔】の塔身は背が低く非常に安定感があります。石造宝塔は、もともと木造宝塔を模したものですから、要所要所で木造の意匠を取り入れています。【満願寺宝塔】の塔身にも高欄(こうらん…欄干・手摺り)・縁板(えんいた…高欄が配置される床部分)が作り出され、また、宝篋印塔の塔身同様に金剛界四仏の種子(梵字)が彫刻されています。
次に屋根ですが、こちらも背が低く非常に安定感があります。そして塔身で説明した通り、木造宝塔を模したものですから、垂木(たるき)や隅木(すみぎ)、降り棟(くだりむね)が意匠として彫刻され、特に降り棟の先の終端に、稚児棟(ちごむね)まで彫刻されているのが圧巻です。
最後に相輪ですが、こちらもしっかり作り込んでいて良い感じです。地方色なのか、相輪の請花(うけばな)が本来の円形ではなく八角形で作られています。こういうちょっとしたところも、見ていて飽きが来ない理由の一つでしょうね。




それと本体以外の繰形座(くりかたざ)と切石積式基壇も丁寧に作り込まれています。特に繰形座はかなり幅が広く、ゆったりとして安定感とやさしさが感じられます。
以上【満願寺宝塔】の魅力を簡単にお話ししましたが、うまく伝わったでしょうか?宝塔の教義(仏塔思想)については、五輪塔・宝篋印塔同様、改めてお話ししたいと思っています。また、いくつかの専門用語が登場しましたので、これらについても後日詳しくご説明できればと思います。
このブログ冒頭に「人生を変えるきっかけとなった一基」とお伝えしましたが、そこについても改めてお話しできればと思います。
以上、質問やご意見がございましたら、どうぞお気軽にコメントやお問い合わせいただければ幸いです。今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。
この記事では、私なりに理解した石造美術について書かせていただきました。もし内容に関して気になる点や誤りがございましたら、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様からのご意見やフィードバックは、今後の改善にとても役立ちますので、どうぞよろしくお願いいたします。