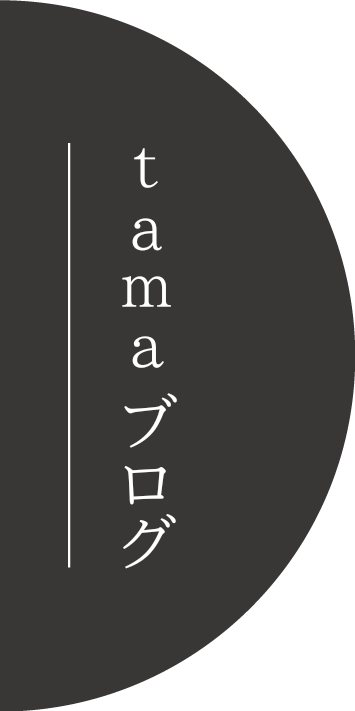こんにちは、たま企画室です。
前回のブログ『千年先に残す功績碑|基礎工事と設計へのこだわり』では「功績碑を支える基礎工事」についてお話ししました。
その基礎の上に据えられる功績碑本体も、制作が無事に終わり、ようやく形となりました。
長い準備を経て完成にたどり着いたことに、私自身もほっとすると同時に、大きな喜びを感じています。
今回は、その制作の過程について少しお話ししてみようと思います。
以前のブログ『風景に寄り添うかたちを探して|功績碑制作、はじまりの一歩』でも触れましたが、この功績碑は「自然のかたちを尊重する」ことを大切にしています。
石そのものの表情や存在感を大切にしつつ、不要な部分をそぎ落として形を整える――そんな考えを軸に、作業を進めてきました。
まずは、デザイナーさんが制作した1/10模型を手元に置きながら、職人さんがトビ矢やエンジンカッターを使って、余分な部分を少しずつ落としていきました。石の全体像を浮かび上がらせるような、最初の大まかな成形作業です。
次に、ノミ切りの作業で形を整えていきます。石の肌に一打ち一打ち刻むことで、輪郭がはっきりと現れ、石本来の風合いが、加工を通じて一層豊かな表情となって浮かび上がってきます。




以前のブログ『功績碑のこと』でもお話ししましたが、功績碑とは、個人や団体の功績を後世に伝えるために建てられる石碑のことです。
今回はとある故人の方の功績を伝える碑であるため、どうすればその方の歩みや想いを訪れる人に身近に感じてもらえるだろうかと、デザインの段階からいろいろと悩みながら制作しました。
著名な方なので私もお名前や存在は存じ上げていましたが、どのような方かということは全く知りませんでした。
そこで、ご子息の雰囲気や社員の方のお話しぶりから、その方がどんな人生を歩まれたのか、自分なりに想像していきました。
穏やかで落ち着いた雰囲気を感じたので、石の形も柔らかなラインを意識し、角もやや丸みを帯びるように加工しました。
そうすることで、まるでその方の人柄が石の中からにじみ出てくるような、やさしい表情が生まれた気がします。






さらに、その方を象徴する「ある印」を石碑の裏面にさりげなく刻みました。
訪れた方がふと目にしたとき、「ああ、この方といえばこれだよね」と感じていただけるような、小さなサインのような存在です。
見つけた人が思わず微笑んでしまうような、そんな仕掛けをこっそり忍ばせています。




そして最後に、目を閉じて石碑全体をそっと素手で撫で、仕上がった肌のやわらかさを確かめました。
石の温もりとともに、その方の人柄がそこに宿ったような感覚がして、ほっと深呼吸したくなるような安らぎがありました。
ここで石碑は私の手からはなれます。あとは風や雨、陽の光、そして訪れる人がそっと手を触れるたびに、この石碑は少しずつ育っていくのでしょう。
長い年月をかけて、石はさらにやわらかさを増し、言葉を持たないままに語りかける存在になっていく――
本来の完成は、これからです。そんな未来を思い描いています。
この先は、実際に石碑を建立した様子や周囲の景観づくり(修景施工)の過程について、今後のブログで順にご紹介していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせください。
今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。