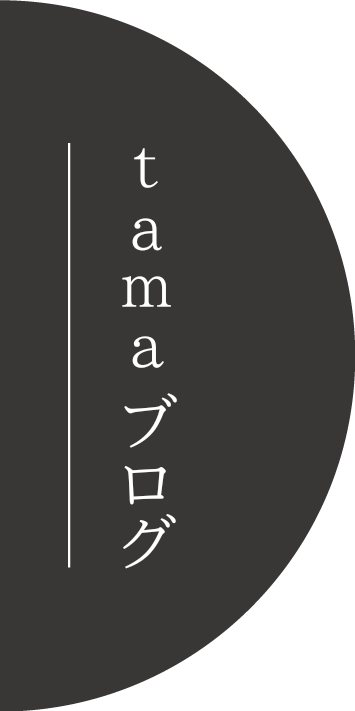こんにちは、たま企画室です。お彼岸も過ぎ、日差しや風がだいぶ秋めいてきましたね。体調を崩しやすい時期でもありますので、皆さまどうぞご自愛ください。
以前のブログ『功績碑のこと』や『風景に寄り添うかたちを探して|功績碑制作、はじまりの一歩』でご紹介した案件がそろそろ完成の時を迎えています。
長い時間をかけて温めてきた計画が少しずつ動き出し、やがて一つの形を成していく――その瞬間に立ち会うと、やはり胸が高鳴ります。
功績碑をしっかりと据えるための基礎工事、そして本体の制作。実際にはそれぞれの作業を同時進行で行いましたが、わかりやすくするため、2回に分けてそれぞれの様子をお伝えします。今回はまず「基礎工事」からです。
基礎工事は、まず地盤調査から始まりました。功績碑を長く安定して支えるために欠かせない、大切な工程です。調査を進めると砂地の部分もありましたが、基礎に影響するほどではなく、問題なく施工できる地盤でした。
基礎の設計・施工は、物理的な根拠に基づき行われています。地盤調査の結果を踏まえて、基礎の面積を広めにとり、功績碑の重さをしっかり分散させるようにしています。使用するコンクリートは、一般の住宅基礎よりやや強い高強度コンクリート(Fc27)。圧縮に強くなるよう設計されているため、基礎自体の耐久性が高まります。さらに、内部の鉄筋を守るために、通常より厚めの保護層(かぶり厚)も確保しました。これにより、鉄筋の腐食リスクを抑え、長期にわたって安心してご使用いただける構造になっています。




加えて、基礎は地中に埋まっている部分がほとんどで、風や雨、紫外線の影響をほとんど受けません。コンクリートの劣化もゆっくり進むため、構造的なリスクは極めて小さく、長く安心してご使用いただけます。
基礎づくりにあたって、私なりに大切にしている考えがあります。石には長い命があると考え、千年先を見据えて設計・施工しています。基礎もただ支えるだけでなく、石をできる限り長く守り続けられるように設計・施工しました。そのため、基礎の面積や強度、鉄筋の保護など、あらゆる条件を整え、耐久性を少しでも高められるよう工夫しています。
もちろん、私なりの工夫を重ねながら設計・施工を進めてまいりましたが、まだ至らない部分もあるかもしれません。それでも、できる限り石を長く支えられるよう心を込めて作業しています。


このように工夫を重ねた基礎ができあがりました。こうして支えられた基礎の上に、次はいよいよ功績碑本体が立ちます。次回は、その制作工程についてご紹介していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせください。
今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。