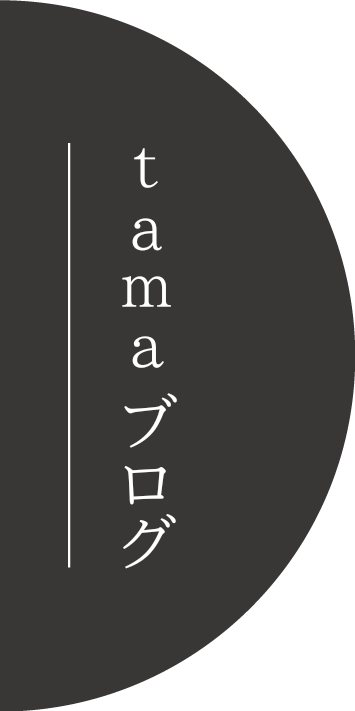こんにちは、たま企画室です。
以前のブログ『「終活」とは未来へのまなざし|職人が語る理想のお墓のかたち』では、功績碑の現場に向かう道中、職人さんとのやり取りの中で感じた「ものづくりの根っこ」のような話を綴りました。
その続きとして、今回はいよいよ本格的に動き始めた功績碑の制作について、背景や込められた思いも交えながらご紹介していきたいと思います。
本記事では、計画の第一歩となる石材の選定に焦点を当てつつ、功績碑づくりのプロセスを少しずつ紐解いてまいります。
当初は、「石碑の制作を担当する」という立場で関わらせていただいておりました。
ところが進行にともない、石材の選定や石碑の意匠設計(※こちらはデザイナーの方とともに進めております)、さらには周囲の修景デザインや現場での調整にまで、思いがけず多くの部分に関わらせていただくこととなりました。
結果的には、全体の監修のような立場でお手伝いさせていただくこととなり、身の引き締まる思いで取り組んでおります。
まず最初のステップは、主役となる石碑の選定です。
今回は、功績碑としての存在感と、周囲の景観との調和――その両方を大切にしたいという思いがありました。
そこで検討したのが、「デザインを施した加工石にするか」、あるいは「自然な形を生かした造形にするか」という方向性の違いです。
前者であれば、意匠性や象徴性をはっきりと打ち出すことができますし、後者であれば、土地の風景にそっと寄り添うような佇まいが生まれます。
どちらにも魅力があり、関係者の皆さまと話し合いながら、慎重に方向性を定めていきました。



結果として、「自然な形を生かした造形」を選ぶことになりました。
その判断の背景には、使用する石材が庵治石であり、丁場にて直接選定できるという利点がありました。
実際に丁場を訪れ、現地で原石の形や質感をじかに確かめたことで、無理なく自然な造形を活かす方向性が、おのずと見えてきたのです。 加工によって形を整えるのではなく、石が本来持っている線や凹凸、表情をそのまま引き出すことで、より土地に馴染み、長く愛される佇まいになるのではないか——そんな想いが、今回の選定を後押ししました。
石と向き合う中で気づかされたのは、「何かを語る石碑」ではなく、「ただ静かにそこに在る」という、その姿そのものに力が宿るということでした。
このように自然のかたちを尊重した石碑は、風景にそっと馴染みながら、時間とともにさらに味わいを深めていく——そんな在り方が、今回の計画にふさわしいのではないかと考えました。




少し長くなってしまいましたので、今回はここまでとさせていただきます。
この先の意匠の背景や設置計画についても、また次回のブログでご紹介してまいりますので、よろしければそちらもお読みいただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせをいただければ幸いです。
今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。