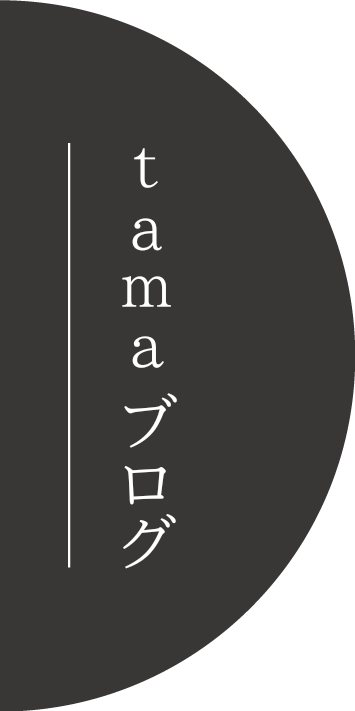_resize_1080.jpg)
こんにちは、たま企画室です。今日は前回のブログ【お正月行事とお墓のつながり|年神様・氏神様を迎える大切な意味】の続きとして、日本の伝統的な風物詩【鏡餅 お年玉のこと】について(今度こそ)、少しお話しさせていただきたいと思います。
まず鏡餅はご存じのように、丸いお餅の大小を重ねたものです。では、なぜお正月に飾るのでしょうか? 勘の良い方は、すでにお気づきかもしれません。鏡餅は家に迎える年神様や氏神様への供物として飾られると同時に、神様が宿る依代(よりしろ)としての役割も果たします。年神様や氏神様は、家族に幸福や健康、豊作をもたらす神様とされ、鏡餅はその神聖な存在を迎え入れるための象徴です。
元々はお餅ではなく、鏡が用いられていたようです。鏡は神を映すものと考えられ、さらに神の依代とされていたからです。
古代から日本では、神様が宿る依代として、特定の物や形が重要視されてきました。鏡はその一つで、神聖な象徴とされます。丸い形の鏡餅も、鏡と同様に神様が降りて宿る神聖な場所とされるのです。
いかがでしょうか?お正月の風物詩とされる門松やしめ飾り、鏡餅は一つとして欠かすことのできない、必要不可欠なものですね。
では最後にお年玉についてです。お年玉は誰もが知るお正月の楽しみです。私なんかはお恥ずかしい話ですが、大人になっても母親や祖母からもらっていました。
どうでも良い話はさておき、お年玉の大事なお話をしましょう。 「んっ!」と思った方はいらっしゃらないと思いますが、【玉(たま)】が含まれていますね。私ども【たま企画室】と同じ【たま】です。
お年玉は、年神様や氏神様からの「魂(たま)」を象徴する贈り物として始まりました。古代では、お年玉は「年魂(としだま)」とも呼ばれ、家長が年神様や氏神様から受け取った恩恵を家族や使用人に分け与える行為でした。
鏡餅は神様の力を宿すと考えられており、その鏡餅を食べることで神様のご加護を受けるという意味合いがありました。この行為が、お年玉の精神的な背景と共通しています。
鏡餅を分け与える行為が形を変え、金銭としての贈り物に発展したと考えられます。江戸時代頃から、お年玉は餅や米などの品物ではなく、お金に形を変えていきました。
現代のお年玉は、袋に入ったお金を子供に渡す形式が一般的ですが、その背景には年神様や氏神様からの恵みを分けるという伝統が根付いています。
良い話でしょう! 日本人の固有信仰には、神様(ご先祖様)を常に身近に感じ、神様に感謝の念や祈りを捧げることで、幸せ(豊作、健康、平和など)という恩恵が授けられるという考え方があります。この信仰の形は一方通行ではなく、神様と人間が互いに幸せを交換し合うような相互作用が特徴です。
お墓も一緒なんですよね! だから私はお墓を作っていると幸せを感じるんです!
さて、もうすぐお正月ですね!
一年の締めくくりを迎えるにあたり、皆様はどのような準備を進められていますか? 年末は忙しさもありますが、家族や大切な方と共に新年を迎える準備をする時間でもありますよね。
たま企画室のブログをご覧いただいている皆様に、今年も心から感謝申し上げます。おかげさまで、たくさんのご縁に恵まれ、充実した一年を過ごすことができました。
新しい年も、皆様の生活に少しでもお役立ちできるようなお話をお届けしてまいります。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
それでは、どうか良いお年をお迎えください!
なお、この記事はこれまでに得た知識をベースに、私の見解や個人的な体験に基づいて書かせていただいております。もし内容に関して気になる点や誤りがあれば、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様のご意見やフィードバックは、今後の改善にとても参考になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせをいただければ幸いです。今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。