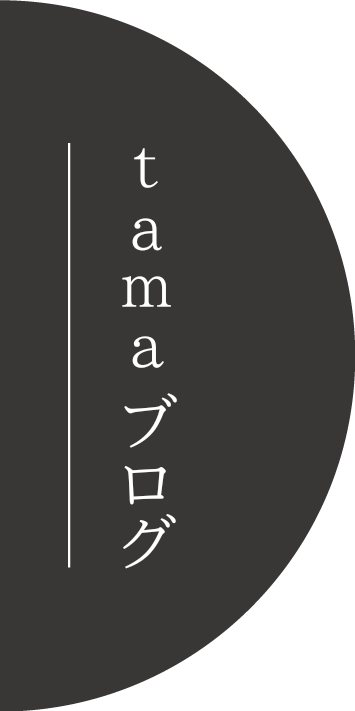_resize_1080.jpg)
こんにちは、たま企画室です。2024年も残すところわずかとなりました。今年もたくさんの方々に支えられ、無事に年末を迎えることができました。本当にありがとうございます。
年の瀬が近づくと、門松やしめ飾り、鏡餅といった迎春の準備が気になる時期でもあります。これらは日本の伝統的な風物詩で、新年を迎えるための大切な役割を果たしますよね。そこで今回は、門松やしめ飾り、鏡餅に込められた意味について、2回に分けて少しお話しさせていただきたいと思います。
まずは、門松についてです。門松とは家の門や玄関に飾られる伝統的な日本の風物詩です。松の枝を中心に竹や梅などを組み合わせて作られ、通常、門の両側に立てられます。
では、どのような意味があるかご存じでしょうか?実は正月における重要な飾り物であり、年神様や氏神様が家々を訪れる際、「ここに迎え入れる準備ができています」という目印として門松を飾ります。この行為は、神様を敬い、幸福や繁栄をもたらしていただくための重要な習慣です。つまりただの飾り物ではなく、「神聖な目印」として用いられてきました。
現代でも門松は、家や建物の入り口に飾ることで年神様や氏神様を迎え入れる正月のシンボルとして親しまれています。
次に、しめ飾りについてお話ししたいと思います。しめ飾りは、年神様や氏神様が家に降り立つための目印として、家の玄関や門に飾られるものです。このしめ飾りも、ただの飾り物ではなく、非常に深い意味が込められています。
まず、しめ飾りの役割ですが、家の入り口を「神聖な場所」として区別するための「結界」としての役割を持っています。つまり、「ここから先は神様が降り立つ場所だよ」という目印として飾られるんですね。新年を迎える準備が整った証であり、年神様や氏神様が降りてきてくれるようにという、家族の願いが込められています。
また、しめ飾りには地域や家庭ごとに少しずつ違いがあり、飾り方にも個性がありますが、どのしめ飾りにも共通しているのは、家族の幸せや健康、繁栄を祈る気持ちが込められていることです。毎年、このような伝統を大切にしながら、新しい年を迎える準備をしていると、心が落ち着き、気持ちが新たになりますね。
なお、この記事はこれまでに得た知識をベースに、私の見解や個人的な体験に基づいて書かせていただいております。もし内容に関して気になる点や誤りがあれば、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様のご意見やフィードバックは、今後の改善にとても参考になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次回のブログでは鏡餅とお年玉について少しお話をさせていただこうと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせをいただければ幸いです。今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。