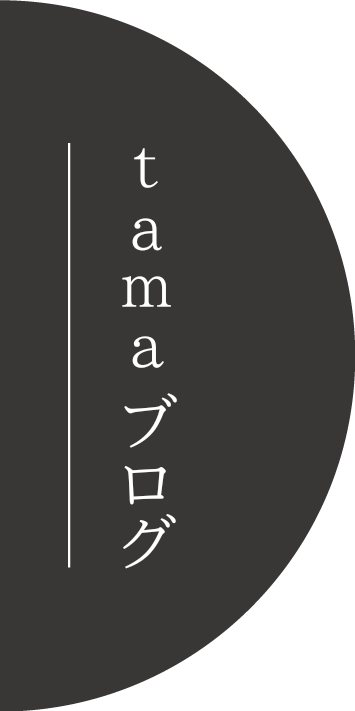こんにちは、たま企画室です。
今日は【石造美術】についてお話ししたいと思います。
今回ご紹介するのは五輪塔ですが、一般的なものとは少し異なり、一つの石から彫り出された五輪塔【一石彫成五輪塔】についてご紹介したいと思います。
「んっ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。特に石造美術に興味のある方や業界の方なら【一石五輪塔】という言葉は聞いたことがあっても、【一石彫成五輪塔】はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで、石造物の紹介の前に【一石彫成五輪塔】について少しお話しします。
一石彫成五輪塔とは?一石五輪塔との違い
【一石五輪塔】とは、室町時代以降、庶民の間でも供養塔が広まる中で、簡略化された小型の供養塔のことを指します。一方で【一石彫成五輪塔】は、それ以前に作られたものとして区別されています。
妙英寺跡の一石彫成五輪塔の概要
今回ご紹介する【一石彫成五輪塔】は、鳥取県東伯郡琴浦町光(みつ)にある【妙英寺跡一石彫成五輪塔】です。
少し話がそれますが、光という集落は【鏝絵(こてえ)】の観光地としても知られています。五輪塔を見学される際は、ぜひ鏝絵も併せてご覧になってみてはいかがでしょうか。



一石彫成五輪塔の特徴
- 現存の高さと推定される元の姿
この五輪塔は現在、空輪と風輪が欠損しており、現存の高さは73.9cmです。火輪(屋根)の上には、別の五輪塔の火輪と水輪が乗せられています。個人的な主観ですが、元は高さ3.0尺塔(90.0cm)で設計されたものではないかと推測しています。 - 初見の印象
初めてこの五輪塔を見たときの感想は、思わず「かわいい!」。50歳のおじさんが言うのもどうかと思いますが、それでもやっぱり「かわいい!」という表現がぴったりですね。 - 各部の特徴
- 地輪(基礎)
通常の五輪塔に比べると、地輪(基礎)が非常に低いですね。このように基礎が低いものは、学術的には「古式」とされています。 - 水輪(塔身)
どっしりとした下膨れの形状をしており、安定感を感じさせます。一方で、角をノミで少し削っただけの簡素な作りに見えます。しかし、そのバランスが絶妙なのでしょうね。いくら見続けても見飽きません。 - 火輪(屋根)
この五輪塔の特徴のひとつが、火輪(屋根)の形状です。通常の五輪塔の火輪(屋根)は、照り(反り)のみで作られるのが一般的です。私が作る五輪塔も、基本的には照り(反り)のみで仕上げます。しかし、この五輪塔は【照り(反り)起くり(てりむくり)】(曲面のうち、重力に従って垂れ下がるように下に反った屋根を「照てり」,逆に重力に逆らって上に膨らむ屋根を「起むくり」と称します。)(注1)で作られています。 - 露盤(ろばん)の存在
ここで、皆さんお気づきでしょうか? 五輪塔なのに、火輪(屋根)の頂上部分に【露盤(ろばん)】が作り出されています。
露盤とは、仏塔(ストゥーパ)や仏教建築の屋根の頂上部分に設置される装飾的な構造物のこと。通常、五輪塔には見られないものですが、この五輪塔にはしっかりと造られています。
この露盤については、改めてブログで詳しくご紹介したいと思います。
- 地輪(基礎)
- 細部に刻まれた四方梵字
そして最後に、この五輪塔の魅力をさらに引き立てているのが、美しく雄大に刻まれた各面の梵字(種子)です。
これらの特徴からも、この五輪塔が室町時代以降の簡略化されたものではなく、かなりしっかりとした注文品であったことが分かります。制作時期は平安時代後期から鎌倉時代前期とされています。
まさに、見落とし厳禁の最高の一石彫成五輪塔ですね!



以上【妙英寺跡一石彫成五輪塔】の魅力を簡単にお話ししましたが、うまく伝わったでしょうか?いくつかの専門用語が登場しましたので、これらについても後日詳しくご説明できればと思います。
質問やご意見がございましたら、どうぞお気軽にコメントやお問い合わせいただければ幸いです。今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。
この記事では、私なりに理解した石造美術について書かせていただきました。もし内容に関して気になる点や誤りがございましたら、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様からのご意見やフィードバックは、今後の改善にとても役立ちますので、どうぞよろしくお願いいたします。
鏝絵(こてえ) とっとり旅HP https://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/204
(注1)引用 大和モダン建築HP https://nara-atlas.com/term/japanese/4391/
参考文献 福澤邦夫著 「伯耆赤碕町の石造文化財(下)」『史跡と美術625号』平成4年6月