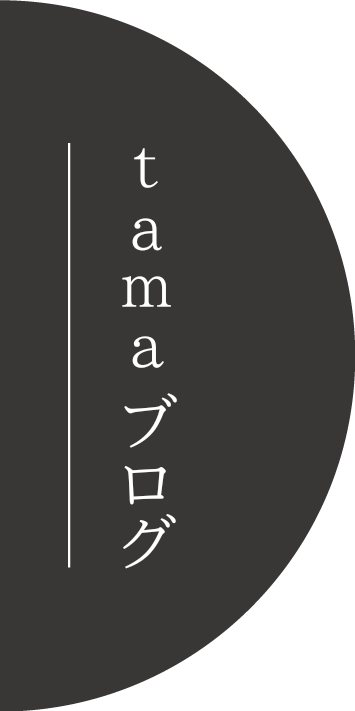_resize_1080.jpg)
こんにちは、たま企画室です。今日は昨日のブログ【正月準備の基本|門松としめ飾りに込められた深い意味を知る】の続きとして、日本の伝統的な風物詩【鏡餅 お年玉のこと】についてお話しさせていただこうと思っていました。しかし「その前に、お伝えすべきことがあるのでは?」と気づきました。私がブログを書き始めて半年ほどですが、これからお話しする内容は、その中でも最も大事なことだと感じていることです。
ところで皆さんは、なぜお正月にお祝いするのかご存じですか? 新しい年を迎えるから、というのももちろんありますが、正月行事は新しい年を迎えるにあたって年神様や氏神様を迎える祭りでもあります。この点を理解していないと、そもそもの意味が分からなくなってしまいますよね。
ただ、お正月の行事は秋祭りのように盛大に行うわけではありません。どちらかといえば、【家々で行う祭り】に近いです。年神様や氏神様を家に迎え入れ、感謝と祈りを捧げるという神聖な行事を執り行います。これは地域の神社などの公的な祭りというよりも、各家庭で行う「家の祭り」に近い性質を持っています。
では、なぜ家で祭りを行うのでしょうか? 迎え入れる年神様や氏神様とは、私たちにとってどのような存在でしょうか? 実は、これらの神様は、ずばり私たちの【ご先祖様】そのものなのです。ご先祖様は、亡くなってから50年(地域によっては33年)ほどかけて魂が浄化され、やがて神格化されて氏神様になると考えられています。また年神様は氏神様とは成り立ちや性質に違いがありますが、日本人の暮らしの中で自然発生的に生まれ、祖霊信仰や農耕文化との結びつきによって重要な役割を担う神様です。つまり、お正月に行う年神様や氏神様を迎え入れる行事は、言い換えれば『ご先祖様を家に迎え入れる行事』といっても過言ではありません。年神様は、新しい年の幸福や豊穣をもたらしてくださる存在であり、氏神様は地域や家族を守り続ける存在として、私たちの暮らしを見守ってくださっています。
家々のご先祖さんを迎え入れるわけですから各家々で行事を執り行うことは、納得できますよね。
結果的にお正月全体の意味を語る回となってしまいましたが、前述しましたように、このことが一番お伝えしたかった内容ですね。そして、この考え方は、お墓の持つ役割そのものに通じる考え方でもあります。お墓もまた、ご先祖様を敬い、感謝を捧げる場であり、家族の絆や祈りの心を形にしたものです。お正月に行う神聖な行事とお墓には、根底で通じ合うものがあるのです。
次回こそ、鏡餅やお年玉についてお話ししたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね!
なお、この記事はこれまでに得た知識をベースに、私の見解や個人的な体験に基づいて書かせていただいております。もし内容に関して気になる点や誤りがあれば、ぜひお気軽にお知らせいただけると幸いです。皆様のご意見やフィードバックは、今後の改善にとても参考になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントやお問い合わせをいただければ幸いです。今後とも、たま企画室をどうぞよろしくお願いいたします。